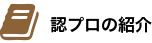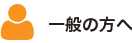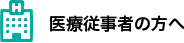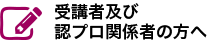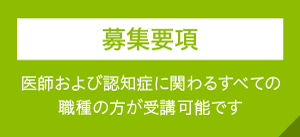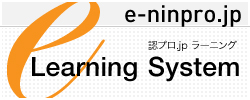各講義の紹介
認知症患者に対しては、生活障害を改善し、地域の中で生活することを支援することが重要である。本授業では、認知症に対する適切なケア、リハビリテーションの基本について学ぶとともに、認知症患者を地域生活の中で支援する制度および実践、認知症診療に関わる法制度や倫理について理解する。
| 第1回 |
認知症のケアとリハビリの基本・原則 |
| 講師 |
木戸幹雄 |
| 所属 |
木戸クリニック |
| 講義内容 |
認知症診療では薬物療法に加えて、生活障害の改善を目的としたケアと、生活能力とQOLの向上を目的とした非薬物療法が重要である。ケアの基本はpersonhood(その人らしさ)を維持することを重視したパーソンセンタードケアである。非薬物療法としては、回想法や現実見当識訓練、芸術療法等がある。認知症に対する非薬物療法は、残存機能を向上させることで二次的に認知機能を向上させることが期待される。 |
| 第2回 |
認知症ケアの実践 |
| 講師 |
島崎正夫 |
| 所属 |
医療法人社団和敬会 谷野呉山病院 |
| 講義内容 |
不適切なケアがBPSDの悪化を招きます。
対応の仕方を工夫することで、認知症の方の不安が少なくなり、介護者の負担も軽減します。
認知症ケアの実践について学びます。 |
| 第3回 |
認知症リハビリの実践 |
| 講師 |
横川正美 |
| 所属 |
金沢大学医薬保健研究域医学系 リハビリテーション科学 |
| 講義内容 |
認知症に対するリハビリテーションの実践として、1)低下する認知機能に直接働きかける、2)残存機能を活かす、3)環境設定について学ぶ。 |
| 第4回 |
社会環境・資源1(認知症に関わる制度・政策) |
| 講師 |
北村立 |
| 所属 |
石川県立こころの病院 |
| 講義内容 |
新オレンジプランの概要を理解し、地域包括支援センターや初期集中支援チーム等の役割を学ぶ。介護保険制度の具体的なサービス内容を理解する。成年後見制度や障害年金制度について学ぶ。 |
| 第5回 |
社会環境・資源2(生活支援と地域連携) |
| 講師 |
北村立 |
| 所属 |
石川県立こころの病院 |
| 講義内容 |
ICF(国際生活機能分類)の概念を学び、生活機能障害という観点から認知症を理解する。認知症の人の生活支援を行うために必要な多職種チームのあり方や訪問看護の実践について学ぶ。 |
| 第6回 |
認知症の人への配慮、法・倫理 |
| 講師 |
北村立 |
| 所属 |
石川県立こころの病院 |
| 講義内容 |
精神保健福祉法における入院手続きを理解する。身体拘束や経済的被害、虐待、自動車運転など認知症を取り巻く社会的問題について学ぶ。認知症の人の医療同意や意思決定について興味を持つ。 |