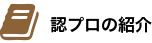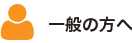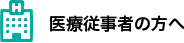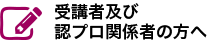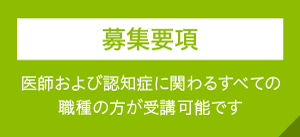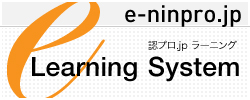各講義の紹介
認知症の基礎を理解するために、認知症の概念、疫学、神経病理学、分子遺伝学、神経化学、神経免疫学、アミロイド-シス分子機構を概説する。| 第1回 | 認知症の概要と疫学 |
|---|---|
| 講師 | 山田正仁 |
| 所属 | 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 |
| 講義内容 | 認知症の定義、原因疾患、疫学など、認知症についての概要を学ぶ。 |
| 第2回 | 認知症の病理学 |
|---|---|
| 講師 | 坂井健二 |
| 所属 | 上越総合病院 神経内科(前:金沢大学附属病院 脳神経内科) |
| 講義内容 | 認知症を生じる疾患は多岐に渡り、神経変性疾患、血管障害や炎症性疾患などが挙げられる。確定診断には病理学的な検索が必要な場合が多い。病理学的な検索には肉眼的な観察、顕微鏡を用いた観察、特殊染色や免疫染色を利用した特徴的構造物や蓄積タンパク質の検索などがある。認知症を生じる疾患の病理について学ぶ。 |
| 第3回 | 認知症の分子遺伝学 |
|---|---|
| 講師 | 濵口毅 |
| 所属 | 金沢医科大学 脳神経内科学(前:金沢大学附属病院 脳神経内科) |
| 講義内容 | 認知症発症に関連する遺伝子多型や認知症発症の原因となる遺伝子変異について学ぶ。 |
| 第4回 | 認知症の神経化学(神経伝達物質)・神経免疫学 |
|---|---|
| 講師 | 岩佐和夫 |
| 所属 | 石川県立看護大学(前:金沢大学大学院 脳老化・神経病態学) |
| 講義内容 | 中枢神経伝達物質の種類と機能について理解し、認知症と神経伝達物質との関連について学ぶ。また、神経細胞の変性過程における神経免疫の関与について理解する。 |
| 第5回 | 認知症の蛋白化学 |
|---|---|
| 講師 | 小野賢二郎 |
| 所属 | 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳神経内科学 |
| 講義内容 | アルツハイマー病やレビー小体型認知症等の病態においてアミロイドβ蛋白やαシヌクレイン蛋白といった蛋白の凝集が深く関わっているとされている。本講義で蛋白凝集と病態に関して概説する。 |
| 第6回 | アミロイドーシスの分子機構 |
|---|---|
| 講師 | 内木宏延 |
| 所属 | 福井大学医学部 分子病理学 |
| 講義内容 | 初めにアミロイドーシスの概念、病理形態学、分類を概説した後、アミロイド線維形成を説明する重合核依存性重合モデルを解説し、このモデルを検証する実験系の概要を述べる。次いでアミロイド線維形成における生体分子の役割に関し、長期血液透析患者に発症するβ2-ミクログロブリンアミロイドーシス、およびアルツハイマー病に認められる脳血管アミロイド症をモデル疾患として解説する。 |